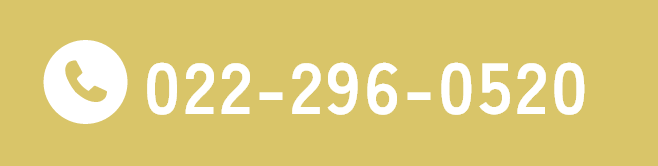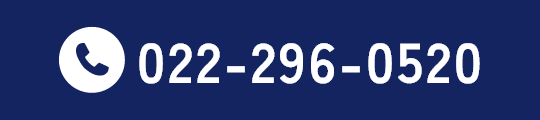アレルギー
アレルギーについて
人体には、細菌やウイルス、寄生虫といった遺物から身体を守る免疫機能があります。この免疫機能が、通常の状態よりも逸脱して外来物質などに強い反応をする状態になったものがアレルギーで、くしゃみなどの上気道症状、口唇の腫れ、や皮膚の発疹や浮腫み、ときには呼吸困難といった深刻な状況を起こすことがあります。
アレルギーの原因物質一覧
吸入性アレルゲン
| 室内塵 | ハウスダスト |
|---|---|
| 家塵ダニ | ヤケヒョウヒダニ |
| コナヒョウヒダニ | |
| 貯蔵庫 ダニ |
アシブトコナダニ |
| サヤアシニクダニ | |
| ケナガコナダニ | |
| イネ科 植物花粉 |
ハルガヤ |
| ギョウギシバ | |
| カモガヤ | |
| ヒロハウシノケグサ | |
| ホソムギ | |
| オオアワガエリ | |
| アシ | |
| ナガハグサ | |
| コヌカグサ(属) | |
| セイバンモロコシ | |
| 小麦(属) | |
| オオスズメノテッポウ | |
| スズメノヒエ(属) | |
| 雑草花粉 | ブタクサ |
| ブタクサモドキ | |
| オオブタクサ | |
| ニガヨモギ | |
| ヨモギ | |
| フランスギク | |
| タンポポ(属) |
| 樹木花粉 | カエデ(属) |
|---|---|
| ハンノキ(属) | |
| シラカンバ(属) | |
| ブナ(属) | |
| ビャクシン(属) | |
| コナラ(属) | |
| ニレ(属) | |
| オリーブ | |
| クルミ(属) | |
| ヤナギ(属) | |
| マツ(属) | |
| スギ | |
| アカシア (属) | |
| ヒノキ | |
| クワ(属) | |
| 真菌/細菌 | ペニシリウム |
| クラドスポリウム | |
| アスペルギルス | |
| ムコール | |
| カンジダ | |
| アルテルナリア | |
| ヘルミントスポリウム | |
| ピティロスポリウム | |
| 黄色ブドウ球菌A | |
| 黄色ブドウ球菌B | |
| トリコフィトン | |
| マラセチア(属) | |
| 動物 | ネコ皮屑 |
| イヌ皮屑 | |
| セキセイインコのふん、羽毛 | |
| ハムスター上皮 |
その他のアレルゲン
| 昆虫 | ミツバチ |
|---|---|
| スズメバチ | |
| アシナガバチ | |
| ゴキブリ | |
| ユスリカ (成虫) | |
| ガ | |
| ヤブカ (属) |
| 寄生虫 | カイチュウ |
|---|---|
| アニサキス | |
| 薬物 | ヒトインスリン |
| ゼラチン | |
| その他 | 綿 |
食品性アレルゲン
| 卵 | 卵白 |
|---|---|
| 卵黄 | |
| オボムコイド | |
| 牛乳 | 牛乳 |
| α-ラクトアルブミン | |
| β-ラクトグロブリン | |
| カゼイン | |
| チーズ | |
| モールドチーズ | |
| 肉 | 豚肉 |
| 牛肉 | |
| 鶏肉 | |
| 羊肉 | |
| 魚介類 | タラ |
| カニ | |
| エビ | |
| ムラサキイガイ | |
| マグロ | |
| サケ | |
| サバ | |
| イカ | |
| タコ | |
| アジ | |
| イワシ | |
| ロブスタ- | |
| アサリ | |
| カレイ | |
| カキ(貝) | |
| ホタテ | |
| イクラ | |
| タラコ | |
| 穀物 | 小麦 |
| ライ麦 | |
| 大麦 | |
| オート麦 | |
| トウモロコシ | |
| 米 | |
| ソバ | |
| キビ | |
| アワ | |
| ヒエ | |
| グルテン | |
| 麦芽 |
| 豆類/ ナッツ |
エンドウ |
|---|---|
| ピーナッツ | |
| 大豆 | |
| インゲン | |
| ハシバミ | |
| ブラジルナッツ | |
| アーモンド | |
| ココナッツ | |
| クルミ | |
| カシューナッツ | |
| カカオ | |
| 果物/野菜 | トマト |
| ニンジン | |
| オレンジ | |
| ジャガイモ | |
| イチゴ | |
| ニンニク | |
| タマネギ | |
| リンゴ | |
| タケノコ | |
| サツマイモ | |
| キウイ | |
| セロリ | |
| パセリ | |
| メロン | |
| マンゴ | |
| バナナ | |
| 洋ナシ | |
| モモ | |
| アボガド | |
| ヤマイモ | |
| グレープフルーツ | |
| ホウレンソウ | |
| カボチャ | |
| スイカ | |
| その他 | ゴマ |
| ビール酵母 | |
| マスタード |
マルチアレルゲン
| イネ科 | 雑草 |
| 動物上皮 | カビ |
| 食物 | 穀物 |
代表的な
アレルギー疾患について
当院では、喘息もアレルギー状態なので喘息やアトピー性皮膚炎、花粉症、食品アレルギーなど、皮膚・鼻・眼に現れるアレルギーを専門に診ています。
アトピー性皮膚炎
アトピー性皮膚炎は、アレルギーを起こしやすい体質の人、皮膚のバリア機能が弱まったタイミングで起こりやすい病気です。主な症状では、かゆみや発疹などが現れます。
特徴は皮膚の発疹とかゆみ、ドライスキンが繰り返して起こって治りにくく、症状の重さとともにアレルギーの検査を行って診断していきます。発疹は、おでこ・目・耳・鼻・口・首、脇や肘、膝の裏側にできやすい傾向にあります。発疹には、肌の赤み、じゅくじゅく感、ひっかくと水が出る、皮膚が硬くなって盛り上がるといった特徴も見られます。
花粉症
スギ花粉がよく知られていますが、このほかヒノキやブタクサ、ヨモギといった約50種類の花粉もアレルギーの原因物質だと言われます。それぞれ開花シーズンが異なるため、年間を通して花粉症に悩む方も多くいます。
花粉症は、花粉と接触して数時間以内に起こります。くしゃみ、鼻水、目や皮膚のかゆみ、胃腸のトラブルや頭痛が現れることもあります。自分のアレルギー原因物質を特定し、その花粉が舞い始める前にお薬を飲み始めると、花粉症の症状はかなり軽くなります。
食品アレルギー
食品に含まれる本来なら無害なたんぱく質を、免疫機能が異常反応して異物として認識し感作されてIgEという抗体をつくって起こす反応が、食品アレルギーの原因になります。卵・牛乳・小麦は3大アレルギー物質といわれ、このほかにも大豆、肉、魚、野菜、果物、ソバやピーナッツが挙げられます。甲殻類アレルギーは重症化リスクが高く、場合によっては、全身にアレルギー反応が出るアナフィラキシー状態に陥るケースもあります。
主な症状は、じんましんや発心、下痢や嘔吐、咳や呼吸困難、粘膜の腫れやかゆみ、せきや呼吸困難でひどいと血圧低下も起こります。原因の食品を摂ってから発症するまでの期間が定まっていないため、治療は、食べたものを記録し、原因の食品を特定するところから始めます。
アレルギー性喘息
慢性的な炎症と、その炎症が原因で過敏になった気道は、喘息の発作を起こしやすい状態になっています。ホコリ、ダニ、花粉などが刺激となって発作が起こり、発作が炎症をさらに悪化させる、といった悪循環を起こすのがアレルギー性喘息です。
喘息は、息苦しさから始まり、しだいに「ヒューヒュー・ゼイセイ」といった喘鳴を伴う発作、呼吸困難や重症の場合には意識不明が起こる状態にまで進行します。症状が軽いうちに治療を始めると治りやすいため、早めにアレルギー科を受診してください。
治療は、吸入のステロイド薬を中心に、抗アレルギー薬など、患者様の症状に即したお薬を処方して行います。
アレルギーの
検査・治療方法について
アレルギーの検査には、血液検査と皮膚検査があります。食品アレルギーが疑われる場合は、別途除去負荷試験を実施します。検査によってアレルギーの原因を特定し、適切な治療を行っていくのですが、食べ物の除去試験や負荷試験は専門的な大きい病院に紹介しています。
アレルギーは体質にも深く関わっているため、完治をめざした治療は難しいといわざるをえません。アレルギーの原因除去・回避、生活習慣改善によって症状を緩和しながら、なるべくアレルギー症状が起こらないように相談しながら治療していきます。